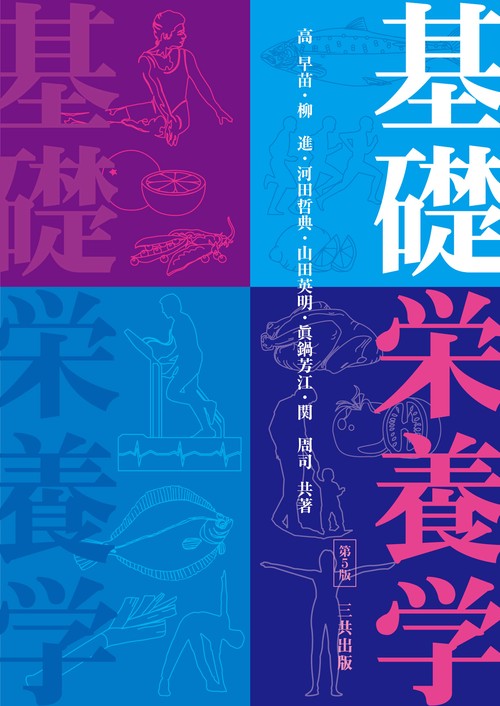- 発売日:2025/04/24
- 出版社:三共出版
- ISBN/JAN:9784782708521
目次
1章 栄養の概念
1-1 栄養と栄養素
1-1-1 栄養とは
1-1-2 栄養素の種類と働き
1-1-3 体構成成分と栄養素
1-2 食品と栄養
1-2-1 食品の定義
1-2-2 食品と栄養素
1-2-3 食品の機能性成分
1-3 健康と栄養
1-3-1 健康の概念
1-3-2 健康に影響を及ぼす要因
1-3-3 栄養素摂取と健康
1-3-4 不適切な栄養素摂取と健康
1-3-5 栄養素摂取の質的評価と健康
1-3-6 適正な栄養素摂取量の目安 ―日本人の食事摂取基準―
1-3-7 ライフステージ別の栄養
1-3-8 わが国の栄養摂取の変遷と疾病
1-4 生活習慣と健康
1-4-1 生活習慣病とは
1-4-2 健康寿命の延伸と一次予防の役割
1-4-3 食習慣の問題点
1-4-4 食生活の指針
1-5 栄養学の歴史
2章 摂食行動
2-1 摂食行動
2-2 摂食調節機構
2-2-1 神経回路機構
2-2-2 体液性調節機構
2-3 食欲に関する感覚と意識
3章 消化・吸収と栄養素の体内動態
3-1 消化器系の構造と機能
3-1-1 食道・胃・小腸・大腸の基本構造
3-1-2 口腔と唾液腺
3-1-3 咽頭と食道
3-1-4 胃
3-1-5 小腸
3-1-6 大腸
3-1-7 肝臓の構造と機能
3-1-8 胆道(胆管・胆嚢)
3-1-9 膵臓
3-2 消化
3-2-1 消化・吸収の基本概念
3-2-2 物理的消化
3-2-3 化学的消化
3-3 吸収
3-3-1 吸収の部位
3-3-2 吸収の機構
3-3-3 各栄養素の吸収
3-4 管内消化の調節
3-4-1 脳相・胃相・腸相
3-4-2 自律神経による調節
3-4-3 消化管ホルモンによる調節
3-5 大腸における吸収・発酵・糞便の形成
3-5-1 大腸における吸収
3-5-2 糞便形成と発酵
3-6 栄養素の体内動態
3-7 生物学的利用度(生物学的有効性:bioavailability)
3-7-1 消化吸収率
3-7-2 栄養価
3-8 サーカディアンリズム(概日リズム)
4章 糖質(炭水化物)の栄養
4-1 糖質とは
4-2 糖質の摂取と消化
4-2-1 日常生活で摂取する糖質
4-2-2 糖質の体内含有量と摂取量
4-2-3 糖質の消化
4-3 糖質の代謝
4-3-1 糖代謝の概略
4-3-2 解糖経路
4-3-3 ペントースリン酸回路
4-3-4 ピルビン酸の代謝
4-3-5 クエン酸回路
4-3-6 グリコーゲン代謝
4-3-7 糖新生
4-4 血糖値の調節
4-4-1 血糖曲線
4-4-2 血糖上昇指数
4-4-3 血糖低下ホルモン
4-4-4 血糖上昇ホルモン
4-5 糖質の栄養
4-5-1 栄養素としての糖質の役割
4-5-2 糖質代謝とビタミンB1
4-5-3 糖質の食事摂取基準
5章 脂質の栄養
5-1 脂質とは
5-2 脂質の摂取と消化
5-2-1 日常生活で摂取される脂質
5-2-2 消化酵素
5-2-3 消化管酵素以外のリパーゼ
5-2-4 脂肪の消化率
5-3 血液中の脂質
5-3-1 リポたんぱく質
5-3-2 リポたんぱく質の種類と役割
5-4 脂肪の酸化
5-4-1 脂肪の動員
5-4-2 脂肪酸酸化の概要
5-4-3 β酸化
5-4-4 β酸化の調節とケトン体
5-4-5 脂肪の合成
5-5 必須脂肪酸
5-5-1 必須脂肪酸の発見
5-5-2 必須脂肪酸の種類
5-5-3 必須脂肪酸の生理機能
5-5-4 必須脂肪酸欠乏症
5-6 リン脂質
5-6-1 リン脂質の分解
5-6-2 リン脂質の生合成
5-7 コレステロール
5-7-1 コレステロールの生理的な役割
5-7-2 コレステロールの生合成
5-7-3 ビタミンD3、ステロイドホルモンと胆汁酸
5-8 エイコサノイド
5-8-1 エイコサノイドの生理作用
5-8-2 エイコサノイドの生合成
5-9 脂質の栄養
5-9-1 体内の脂肪貯蔵
5-9-2 エネルギー源としての脂肪
5-9-3 脂質の摂取量
5-9-4 コレステロール
6章 たんぱく質の栄養
6-1 たんぱく質・アミノ酸の化学
6-1-1 たんぱく質の構造と分類
6-1-2 アミノ酸の構造と分類
6-2 たんぱく質・アミノ酸の役割
6-2-1 たんぱく質
6-2-2 オリゴペプチド
6-2-3 アミノ酸の役割
6-3 たんぱく質・アミノ酸の代謝
6-3-1 たんぱく質の代謝
6-3-2 アミノ酸の代謝
6-4 たんぱく質の栄養
6-4-1 食品たんぱく質の栄養価
6-4-2 食品たんぱく質の栄養評価法
6-4-3 食品たんぱく質の栄養価
6-4-4 アミノ酸の補足効果
6-4-5 たんぱく質の食事摂取基準
7章 ビタミンの栄養
7-1 ビタミンの種類と分類
7-1-1 ビタミンの定義
7-1-2 ビタミンの種類と分類
7-2 脂溶性ビタミン
7-2-1 ビタミンA
7-2-2 ビタミンD
7-2-3 ビタミンE
7-2-4 ビタミンK
7-3 水溶性ビタミン
7-3-1 ビタミンB1
7-3-2 ビタミンB2
7-3-3 ビタミンB6
7-3-4 ナイアシン
7-3-5 パントテン酸
7-3-6 ビオチン
7-3-7 葉酸
7-3-8 ビタミンB12
7-3-9 ビタミンC
7-4 ビタミン様作用物質
8章 無機質(ミネラル)の栄養
8-1 無機質(ミネラル)とは
8-2 無機質の機能
8-3 主要元素
8-3-1 カルシウム(Ca;Calcium)
8-3-2 リン(P;Phosphorus)
8-3-3 マグネシウム(Mg;Magnesium)
8-3-4 ナトリウム(Na;Sodium)
8-3-5 カリウム(K;Potassium)
8-3-6 塩素(Cl;Chlorine)
8-3-7 イオウ(S;Sulfur)
8-4 微量元素
8-4-1 鉄(Fe;Iron)
8-4-2 銅(Cu;Copper)
8-4-3 亜鉛(Zn;Zinc)
8-4-4 セレン(Se;Selenium)
8-4-5 マンガン(Mn;Manganese)
8-4-6 ヨウ素(I;iodine)
8-4-7 クロム(Cr;Chromium)
8-4-8 モリブデン(Mo;Molybdenum)
8-4-9 コバルト(Co;Cobalt)
8-4-10 フッ素(F;Fluorine)
9章 水、電解質の代謝
9-1 水の分布
9-2 水の機能
9-3 水の出納
9-4 水の欠乏と過剰
9-5 水の排泄調節
9-6 運動と水分平衡
9-7 電解質の分布
10章 機能性非栄養素成分
10-1 食物繊維
10-2 食物繊維の定義
10-3 食物繊維の生理作用
10-4 食物繊維の食事摂取基準
10-5 難消化性糖類
11章 エネルギー代謝
11-1 エネルギー
11-1-1 エネルギー代謝
11-1-2 エネルギー量を表す単位
11-2 自由エネルギーの獲得
11-2-1 電子伝達系におけるATP合成
11-2-2 グルコースのエネルギー転換効率
11-2-3 エネルギー消費とATPの合成
11-3 エネルギーの供給
11-3-1 三大熱量素のエネルギー量
11-3-2 エネルギー換算係数
11-4 エネルギーの産生
11-4-1 呼吸商(RQ)
11-4-2 エネルギー消費量の測定
11-4-3 エネルギー代謝と酸素供給
11-4-4 活性酸素の生成と消去
11-5 エネルギー必要量
11-5-1 基礎代謝
11-5-2 安静時代謝(REE)
11-5-3 食事誘発性熱産生
11-5-4 活動代謝
12章 遺伝子発現と栄養
12-1 遺伝情報
12-2 遺伝形質と栄養の相互作用
12-2-1 遺伝子の構造、遺伝情報の発現および発現調節
12-2-2 栄養素に対する応答の個人差の遺伝的背景
12-2-3 遺伝子病(狭義の遺伝病)
12-2-4 生活習慣病と遺伝子多型
12-3 後天的遺伝子変異と栄養素・非栄養素成分
12-3-1 がんのプロモーション、イニシエーションの抑制
付録
1 日本人の食事摂取基準(2025年版)
2 食事バランスガイド
1-1 栄養と栄養素
1-1-1 栄養とは
1-1-2 栄養素の種類と働き
1-1-3 体構成成分と栄養素
1-2 食品と栄養
1-2-1 食品の定義
1-2-2 食品と栄養素
1-2-3 食品の機能性成分
1-3 健康と栄養
1-3-1 健康の概念
1-3-2 健康に影響を及ぼす要因
1-3-3 栄養素摂取と健康
1-3-4 不適切な栄養素摂取と健康
1-3-5 栄養素摂取の質的評価と健康
1-3-6 適正な栄養素摂取量の目安 ―日本人の食事摂取基準―
1-3-7 ライフステージ別の栄養
1-3-8 わが国の栄養摂取の変遷と疾病
1-4 生活習慣と健康
1-4-1 生活習慣病とは
1-4-2 健康寿命の延伸と一次予防の役割
1-4-3 食習慣の問題点
1-4-4 食生活の指針
1-5 栄養学の歴史
2章 摂食行動
2-1 摂食行動
2-2 摂食調節機構
2-2-1 神経回路機構
2-2-2 体液性調節機構
2-3 食欲に関する感覚と意識
3章 消化・吸収と栄養素の体内動態
3-1 消化器系の構造と機能
3-1-1 食道・胃・小腸・大腸の基本構造
3-1-2 口腔と唾液腺
3-1-3 咽頭と食道
3-1-4 胃
3-1-5 小腸
3-1-6 大腸
3-1-7 肝臓の構造と機能
3-1-8 胆道(胆管・胆嚢)
3-1-9 膵臓
3-2 消化
3-2-1 消化・吸収の基本概念
3-2-2 物理的消化
3-2-3 化学的消化
3-3 吸収
3-3-1 吸収の部位
3-3-2 吸収の機構
3-3-3 各栄養素の吸収
3-4 管内消化の調節
3-4-1 脳相・胃相・腸相
3-4-2 自律神経による調節
3-4-3 消化管ホルモンによる調節
3-5 大腸における吸収・発酵・糞便の形成
3-5-1 大腸における吸収
3-5-2 糞便形成と発酵
3-6 栄養素の体内動態
3-7 生物学的利用度(生物学的有効性:bioavailability)
3-7-1 消化吸収率
3-7-2 栄養価
3-8 サーカディアンリズム(概日リズム)
4章 糖質(炭水化物)の栄養
4-1 糖質とは
4-2 糖質の摂取と消化
4-2-1 日常生活で摂取する糖質
4-2-2 糖質の体内含有量と摂取量
4-2-3 糖質の消化
4-3 糖質の代謝
4-3-1 糖代謝の概略
4-3-2 解糖経路
4-3-3 ペントースリン酸回路
4-3-4 ピルビン酸の代謝
4-3-5 クエン酸回路
4-3-6 グリコーゲン代謝
4-3-7 糖新生
4-4 血糖値の調節
4-4-1 血糖曲線
4-4-2 血糖上昇指数
4-4-3 血糖低下ホルモン
4-4-4 血糖上昇ホルモン
4-5 糖質の栄養
4-5-1 栄養素としての糖質の役割
4-5-2 糖質代謝とビタミンB1
4-5-3 糖質の食事摂取基準
5章 脂質の栄養
5-1 脂質とは
5-2 脂質の摂取と消化
5-2-1 日常生活で摂取される脂質
5-2-2 消化酵素
5-2-3 消化管酵素以外のリパーゼ
5-2-4 脂肪の消化率
5-3 血液中の脂質
5-3-1 リポたんぱく質
5-3-2 リポたんぱく質の種類と役割
5-4 脂肪の酸化
5-4-1 脂肪の動員
5-4-2 脂肪酸酸化の概要
5-4-3 β酸化
5-4-4 β酸化の調節とケトン体
5-4-5 脂肪の合成
5-5 必須脂肪酸
5-5-1 必須脂肪酸の発見
5-5-2 必須脂肪酸の種類
5-5-3 必須脂肪酸の生理機能
5-5-4 必須脂肪酸欠乏症
5-6 リン脂質
5-6-1 リン脂質の分解
5-6-2 リン脂質の生合成
5-7 コレステロール
5-7-1 コレステロールの生理的な役割
5-7-2 コレステロールの生合成
5-7-3 ビタミンD3、ステロイドホルモンと胆汁酸
5-8 エイコサノイド
5-8-1 エイコサノイドの生理作用
5-8-2 エイコサノイドの生合成
5-9 脂質の栄養
5-9-1 体内の脂肪貯蔵
5-9-2 エネルギー源としての脂肪
5-9-3 脂質の摂取量
5-9-4 コレステロール
6章 たんぱく質の栄養
6-1 たんぱく質・アミノ酸の化学
6-1-1 たんぱく質の構造と分類
6-1-2 アミノ酸の構造と分類
6-2 たんぱく質・アミノ酸の役割
6-2-1 たんぱく質
6-2-2 オリゴペプチド
6-2-3 アミノ酸の役割
6-3 たんぱく質・アミノ酸の代謝
6-3-1 たんぱく質の代謝
6-3-2 アミノ酸の代謝
6-4 たんぱく質の栄養
6-4-1 食品たんぱく質の栄養価
6-4-2 食品たんぱく質の栄養評価法
6-4-3 食品たんぱく質の栄養価
6-4-4 アミノ酸の補足効果
6-4-5 たんぱく質の食事摂取基準
7章 ビタミンの栄養
7-1 ビタミンの種類と分類
7-1-1 ビタミンの定義
7-1-2 ビタミンの種類と分類
7-2 脂溶性ビタミン
7-2-1 ビタミンA
7-2-2 ビタミンD
7-2-3 ビタミンE
7-2-4 ビタミンK
7-3 水溶性ビタミン
7-3-1 ビタミンB1
7-3-2 ビタミンB2
7-3-3 ビタミンB6
7-3-4 ナイアシン
7-3-5 パントテン酸
7-3-6 ビオチン
7-3-7 葉酸
7-3-8 ビタミンB12
7-3-9 ビタミンC
7-4 ビタミン様作用物質
8章 無機質(ミネラル)の栄養
8-1 無機質(ミネラル)とは
8-2 無機質の機能
8-3 主要元素
8-3-1 カルシウム(Ca;Calcium)
8-3-2 リン(P;Phosphorus)
8-3-3 マグネシウム(Mg;Magnesium)
8-3-4 ナトリウム(Na;Sodium)
8-3-5 カリウム(K;Potassium)
8-3-6 塩素(Cl;Chlorine)
8-3-7 イオウ(S;Sulfur)
8-4 微量元素
8-4-1 鉄(Fe;Iron)
8-4-2 銅(Cu;Copper)
8-4-3 亜鉛(Zn;Zinc)
8-4-4 セレン(Se;Selenium)
8-4-5 マンガン(Mn;Manganese)
8-4-6 ヨウ素(I;iodine)
8-4-7 クロム(Cr;Chromium)
8-4-8 モリブデン(Mo;Molybdenum)
8-4-9 コバルト(Co;Cobalt)
8-4-10 フッ素(F;Fluorine)
9章 水、電解質の代謝
9-1 水の分布
9-2 水の機能
9-3 水の出納
9-4 水の欠乏と過剰
9-5 水の排泄調節
9-6 運動と水分平衡
9-7 電解質の分布
10章 機能性非栄養素成分
10-1 食物繊維
10-2 食物繊維の定義
10-3 食物繊維の生理作用
10-4 食物繊維の食事摂取基準
10-5 難消化性糖類
11章 エネルギー代謝
11-1 エネルギー
11-1-1 エネルギー代謝
11-1-2 エネルギー量を表す単位
11-2 自由エネルギーの獲得
11-2-1 電子伝達系におけるATP合成
11-2-2 グルコースのエネルギー転換効率
11-2-3 エネルギー消費とATPの合成
11-3 エネルギーの供給
11-3-1 三大熱量素のエネルギー量
11-3-2 エネルギー換算係数
11-4 エネルギーの産生
11-4-1 呼吸商(RQ)
11-4-2 エネルギー消費量の測定
11-4-3 エネルギー代謝と酸素供給
11-4-4 活性酸素の生成と消去
11-5 エネルギー必要量
11-5-1 基礎代謝
11-5-2 安静時代謝(REE)
11-5-3 食事誘発性熱産生
11-5-4 活動代謝
12章 遺伝子発現と栄養
12-1 遺伝情報
12-2 遺伝形質と栄養の相互作用
12-2-1 遺伝子の構造、遺伝情報の発現および発現調節
12-2-2 栄養素に対する応答の個人差の遺伝的背景
12-2-3 遺伝子病(狭義の遺伝病)
12-2-4 生活習慣病と遺伝子多型
12-3 後天的遺伝子変異と栄養素・非栄養素成分
12-3-1 がんのプロモーション、イニシエーションの抑制
付録
1 日本人の食事摂取基準(2025年版)
2 食事バランスガイド